オザケン@京都会館その1。その夜ニューヨークは真っ暗だった。
だけど、僕は上を向いて天井を眺めていた。
ステージの上から緩やかなドーム状のカーブを描いているはずの真っ暗な天井を。
会場は真っ暗だ。
ステージの上にだけ、微かなスポットライトが落ちていて、その小さな光の中に彼は立っていた。彼はニューヨークで起こった停電のことを話していた。2003年の夏、ニューヨークでは大規模な停電が起こり、設備の大半を電力で動かしている世界一番巨大な街は機能を停止した。交通網と通信網を失った街には、家へ帰ることのできない人々が溢れた。停電はニューヨークだけではなく北米とカナダにまで広がっていて、復旧の見通しは一晩なかった。
その夜の話だ。
電気がないと動かない、世界で一番大きな街が電気を失い、そんな中で真っ暗な一晩を過ごすのは恐ろしいことなのかもしれない。
でも、彼が語ったのはそういった恐怖とは別の話だった。
電気のない街にはロウソクが灯り始めた。冷蔵庫が動かなくてどうせ腐るからと、食料品店がただで食品を配り、ロウソクの灯りで人々がそれを調理した。周囲の状況に耳を澄ませ、困っていそうな人を助けたり、感じの合いそうな人を探したり。
テレビの代わりに電池で動くラジオが大活躍した。ラジオからは音楽が流れていた。
そうして、人々は真っ暗な大都会で一夜限りのパーティーを始めた。
それは、もしかしたらこうであったかもしれない別の世界の在り方だった。いつもとは全然違う、別の可能性だった。僕達はそういう風に、それぞれが助け合い、みんなで音楽を聞いて、ロウソクの灯りの下で食事をして、って風にも暮らせたのかもしれない。
夜が明ければ、一夜限りのパーティーは終わり、人々は忙しいニューヨークの日常へ戻っていく。
だけど、一度見た、その別の世界のことを、別の在り方のことを、別の可能性のことを忘れることはない。
ステージの上で、小沢健二はそういうことを朗読していた。僕は生まれて初めて目にするその人の方を見れば良かったのかもしれない。小さな光の灯るステージの上を。
だけど、僕は天上を見ていた。
朗読が終わると音楽が演奏され、そして真っ暗闇という停電の演出は終わり、豊かな明かりがステージを照らし出す。今は遠目にもはっきりと小沢健二の姿が見えた。
ステージから溢れた光は僕の眺めていた天井へも届き、前川國男がデザインした曲面に豊かな陰を落とした。
1960年の完成以来、きっと一度も日の光を浴びずに、数々のステージを見守ってきたこの天井はさっき小沢健二が読み上げた朗読をどのように聞いたのだろう。
一夜限りのパーティーが始まる。
(その2へ続く)
ステージの上から緩やかなドーム状のカーブを描いているはずの真っ暗な天井を。
会場は真っ暗だ。
ステージの上にだけ、微かなスポットライトが落ちていて、その小さな光の中に彼は立っていた。彼はニューヨークで起こった停電のことを話していた。2003年の夏、ニューヨークでは大規模な停電が起こり、設備の大半を電力で動かしている世界一番巨大な街は機能を停止した。交通網と通信網を失った街には、家へ帰ることのできない人々が溢れた。停電はニューヨークだけではなく北米とカナダにまで広がっていて、復旧の見通しは一晩なかった。
その夜の話だ。
電気がないと動かない、世界で一番大きな街が電気を失い、そんな中で真っ暗な一晩を過ごすのは恐ろしいことなのかもしれない。
でも、彼が語ったのはそういった恐怖とは別の話だった。
電気のない街にはロウソクが灯り始めた。冷蔵庫が動かなくてどうせ腐るからと、食料品店がただで食品を配り、ロウソクの灯りで人々がそれを調理した。周囲の状況に耳を澄ませ、困っていそうな人を助けたり、感じの合いそうな人を探したり。
テレビの代わりに電池で動くラジオが大活躍した。ラジオからは音楽が流れていた。
そうして、人々は真っ暗な大都会で一夜限りのパーティーを始めた。
それは、もしかしたらこうであったかもしれない別の世界の在り方だった。いつもとは全然違う、別の可能性だった。僕達はそういう風に、それぞれが助け合い、みんなで音楽を聞いて、ロウソクの灯りの下で食事をして、って風にも暮らせたのかもしれない。
夜が明ければ、一夜限りのパーティーは終わり、人々は忙しいニューヨークの日常へ戻っていく。
だけど、一度見た、その別の世界のことを、別の在り方のことを、別の可能性のことを忘れることはない。
ステージの上で、小沢健二はそういうことを朗読していた。僕は生まれて初めて目にするその人の方を見れば良かったのかもしれない。小さな光の灯るステージの上を。
だけど、僕は天上を見ていた。
朗読が終わると音楽が演奏され、そして真っ暗闇という停電の演出は終わり、豊かな明かりがステージを照らし出す。今は遠目にもはっきりと小沢健二の姿が見えた。
ステージから溢れた光は僕の眺めていた天井へも届き、前川國男がデザインした曲面に豊かな陰を落とした。
1960年の完成以来、きっと一度も日の光を浴びずに、数々のステージを見守ってきたこの天井はさっき小沢健二が読み上げた朗読をどのように聞いたのだろう。
一夜限りのパーティーが始まる。
(その2へ続く)
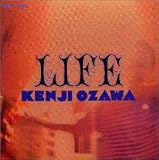 | LIFE |
| クリエーター情報なし | |
| EMIミュージック・ジャパン |
 | 建築家・前川國男の仕事 |
| クリエーター情報なし | |
| 美術出版社 |